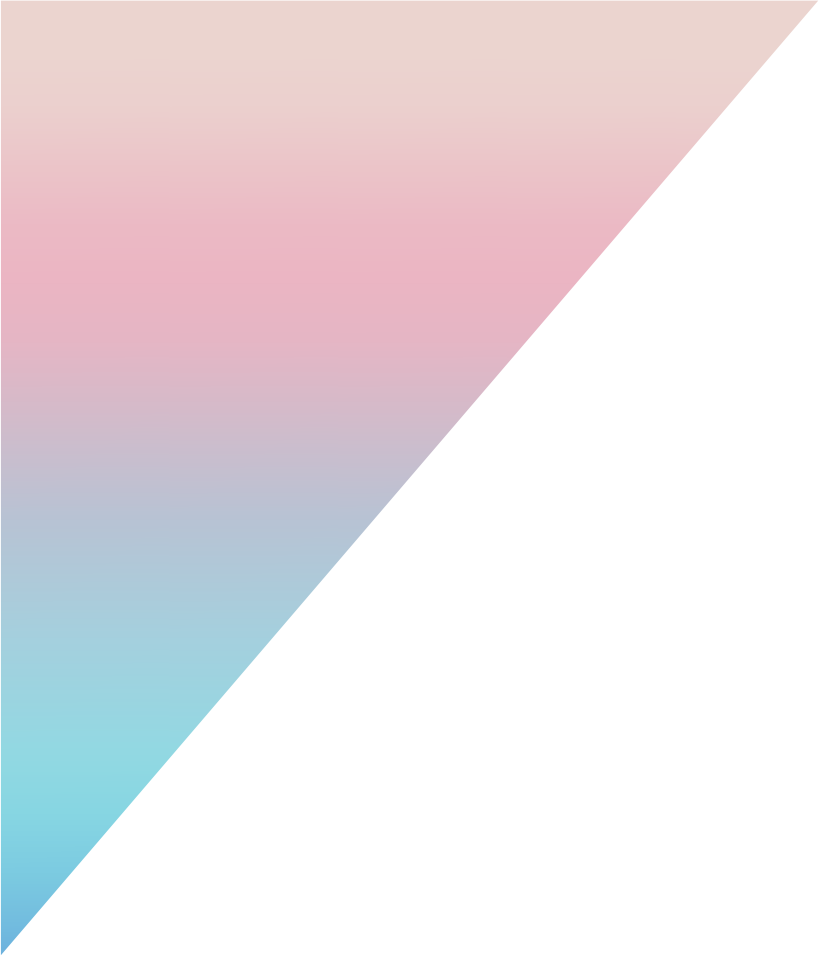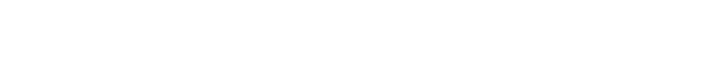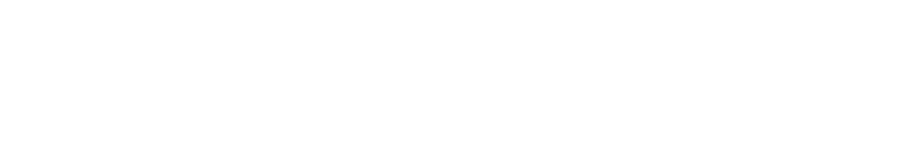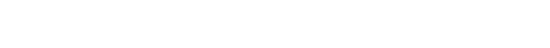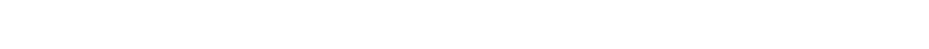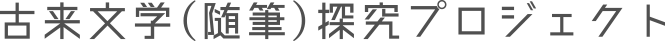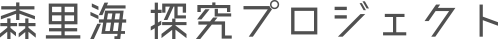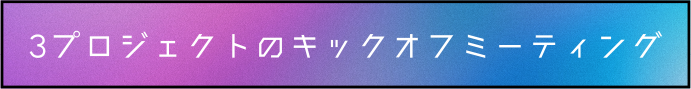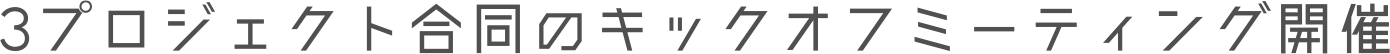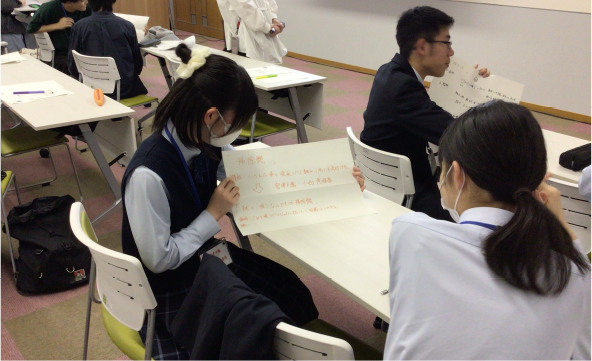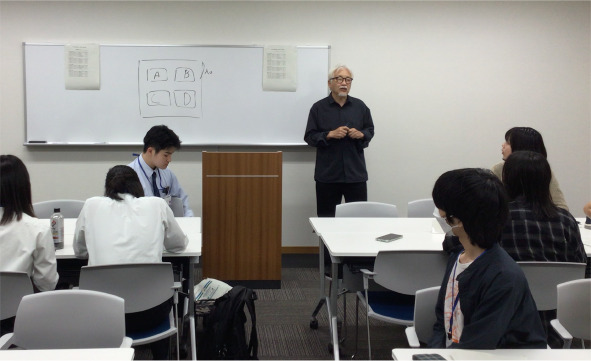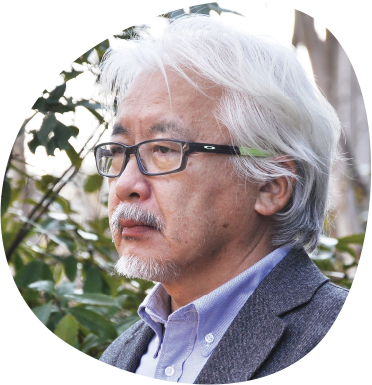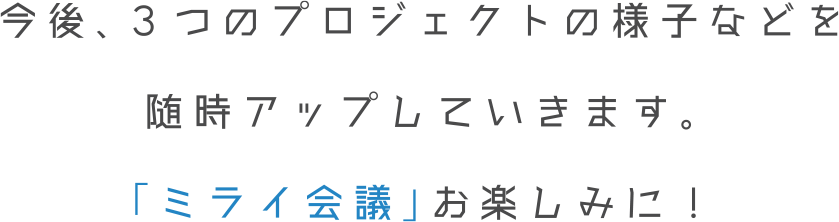vol.16.21sat
@午前:府立京都学・歴彩館
午後:府立植物園
古来文学(古今和歌集、枕草子、徒然草等)において、動植物がどのように描かれ、筆者等が触れ合い、感じているのかなどを学ぶとともに、府立植物園で古来文学に登場する植物の観察を通じた、和歌作りを行います。
 出典: ColBase (https://colbase.nich.go.jp/)をもとに作成
出典: ColBase (https://colbase.nich.go.jp/)をもとに作成
vol.28.2sat
@午前:嵯峨嵐山(桂川河川敷)
午後:京都御所、京都迎賓館、SASAYAIORI+ 京都御苑等
動植物生息地における虫の音観賞はじめ、文学ゆかりの京都御所等の見学、また植物にちなんだ和菓子作りを行います。